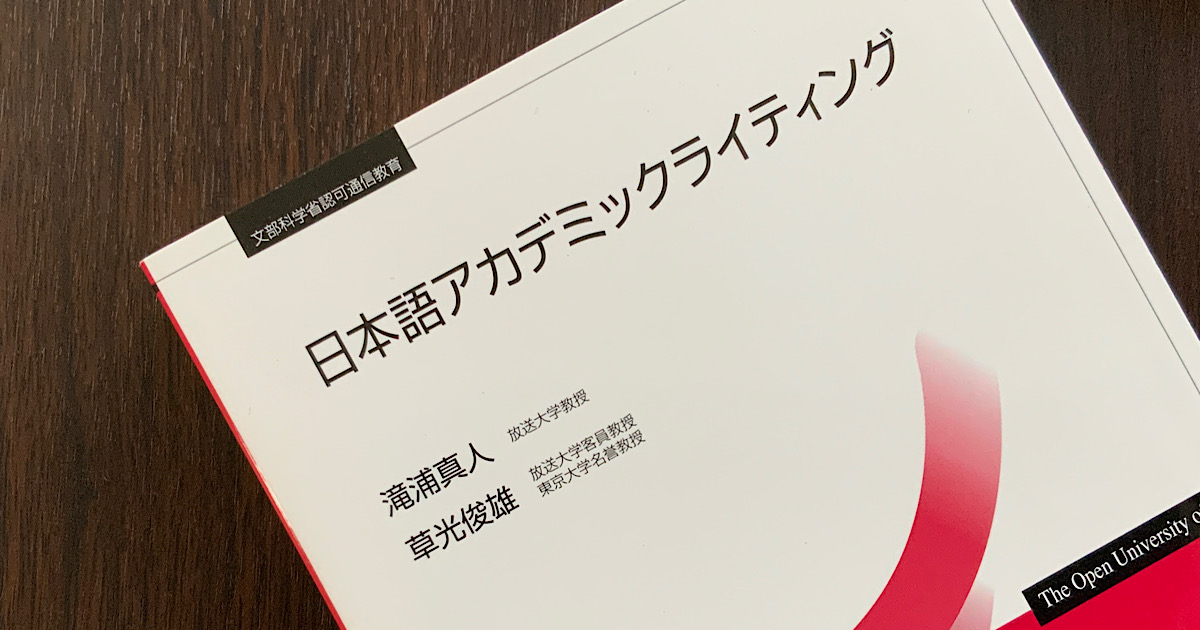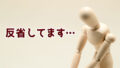2021年第1期に受講、入学して最初の科目登録のひとつです。
大学ではレポートや論文を書く時があるだろう事から、日本語リテラシーと共に科目登録は必須と判断しました。
論文に限らず、文章を書く上でとても勉強になる授業でした。
授業概要
日本語での学術的な文章、いわゆる論文を書くには何が必要かを学んでいきます。
調べ方、ツールの使い方、論理的な文章の書き方、引用や考察の仕方など、論文を書くためのプロセスを段階を追って学んでいきます。
芸術的な”うまい文章”ではなく、実用的な”わかる文章”を書く事を目指します。
| コース・科目 | 基盤科目 |
| 放送形式 | ラジオ放送 45分×15回 |
| 主任講師 | 滝浦 真人(放送大学教授)、草光 俊雄(東京大学名誉教授) |
| 単位認定試験 | 択一式 |
目次
第1回 何のために書くか
第2回 わかる文章とは?
第3回 客観的な文章
第4回 タイトルまで
第5回 問題意識と観点の整理
第6回 情報を調べる
第7回 「他者の言葉」で書く
第8回 パラグラフで書く
第9回 文のつくり方
第10回 根拠を挙げる
第11回 調査結果を利用する
第12回 理科系の文章
第13回 社会科学の文体
第14回 考察と結論
第15回 アカデミックライティングとは何か
感想
滝浦先生が「のんびりした感じの喫茶店のおしゃべり」とおっしゃってましたが、確かにそのような雰囲気の授業でした。
パートごとに様々な先生が登場され、授業が進んでいきます。
第11章では、岩永学長も登場します。
入学して初めての科目の一つでもあったので、自分の勉強の仕方がまだよくわからず、ただひたすら聞いていたという感じでしたが、今は論文をバリバリ書かれている先生がたも、作文が苦手だったというエピソードなどもあり、楽しい授業でした。
ラジオ放送なので、視覚に惑わされず耳だけで聞いていたので、それも良かったと思います。
「日本語リテラシー」「アカデミックライティング」両方を学んで、これまでいかに独りよがりの文章を書いてきたか気付かされました。
振り返ってみると、会社の報告書も、客観的な文章ではなく、どこかしら自分の思いを伝えようという感情的な意図が入っていたように思います。
いわゆる、論文にはストーリーで使われる「起承転結」はいらないという事です。
あとは、先生方皆さん英語が得意なのも当然といえば当然なのでしょうが、論文を書くにはやはり英語ができてなんぼなんだなと実感しました。
ちなみに主任講師の滝浦先生は東大卒で言語学者、草光先生は英国史学者で東大名誉教授だそうです。
テキストの裏に主任講師の経歴が書かれており、そのすごさに毎度驚かされますが、様々なステージで勉強を重ねてきた素晴らしい先生方に教えていただけるのは本当にありがたい事です。
日本語リテラシーと共に、アカデミックライティングもとても良い授業でした。
難しかったですけどね。
単位認定試験
結果は◯Aで無事合格できました。
択一式で、4問の中から正解を選ぶ形式です。
試験問題は親切で、「印刷教材第1章の~」といった感じで、参照する章の案内があるのでテキストからも探しやすく、他の学生の感想も読んだりしましたが難易度は低いようです。
2022年リニューアル
2022年には新たな「日本語アカデミックライティング(’22)」が登場しました。
放送大学の科目はだいたい4~6年の放送スパンなので、そのタイミングだったんですね。
ラジオからテレビになり、新たに追加された項目もありで、装いも新たに今回は贅沢にも放送大学全コースの先生方が参加されて、より充実した授業になっているようです。
そしてなんと、この授業は一般放送はされず、放送大学の学生のみが受けられる授業だそうです。
「日本語アカデミックライティング(’17)」単位取得者は履修不可とは書かれていなかったので、ぜひ受けたいと考えています。
ラジオの時は見れませんでしたが、滝浦先生のファッションも楽しみです。
まとめ
学術的な文章(論文)の書き方が学べます。
放送大学生なら一度は受けておくべき科目です。
2022年から学生限定のテレビ授業になりました。