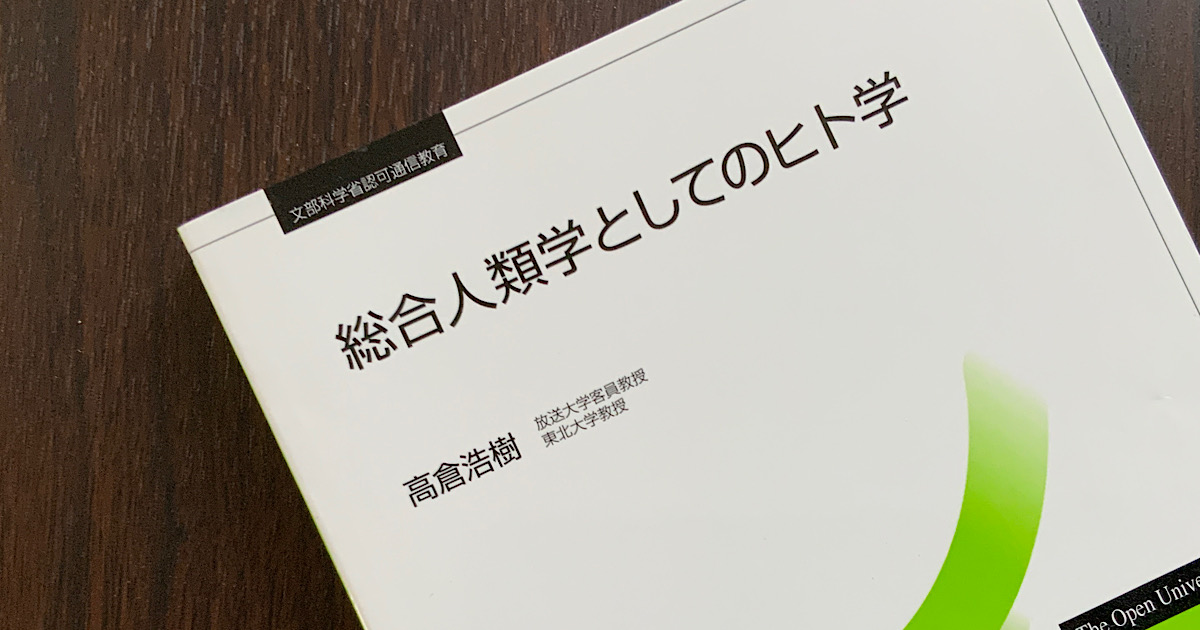総合人類学という立派なタイトルに釣られ、受けてみました。
結果はヒトに関わる様々な学問が学べる、お得で面白い科目でした。
授業概要
簡単に言えば、ヒト(人)を理解するための科目です。
文化人類学、生物学、考古学、霊長類学など、ヒトに関する様々な学問の、知識や見解、考え方を総合する事により、ヒトの全体像を把握していきます。
| コース・科目 | 人間と文化 導入科目 |
| 放送形式 | ラジオ放送 45分×15回 |
| 主任講師 | 高倉 浩樹(東北大学教授) |
| 単位認定試験 | 択一式 |
目次
第1回 地球におけるヒトの存在
第2回 文化としてのドメスティケーション
第3回 からだの進化
第4回 食べものをとる
第5回 家畜とともに暮らす
第6回 食べものをつくりだす技と場
第7回 ヒトの家族の起源
第8回 ヒトの繋がりと社会集団
第9回 時間と空間を区切る
第10回 遊ぶことと祈ること
第11回 もののやりとりと社会関係
第12回 支配の仕組み
第13回 近代世界の成立と国民国家の形成
第14回 グローバリゼーションとローカル社会
第15回 地球温暖化と人類社会
感想
ヒトを研究する分野にも、多種多様な学問がある事を知りました。
内容的には、自分もヒトの1人なので理解しやすかったです。
エネルギー、農業、牧畜、家族、遊び、支配、気候など、様々な観点からヒトというものを見ていきます。
災害人類学という学問があることも初めて知りました。
各章それぞれ興味深かったのですが、第14回 5章の「グローバリゼーションの諸相 ツバルのフィールドワークから」は面白かったです。
※グローバリゼーション:地球規模の移動
この章では、ローカル社会(狭い限られた社会)を主な研究にしがちな人類学に、今後求められるであろうグローバリゼーションについて描かれていました。
ざっくりと説明すると、
ツバルという国は、数多くの小さな島々から構成されており、最近では温暖化による海面上昇で注目を集めています。
メディアは、島の住人を、海面上昇で沈んでしまう可哀想な被害者として捉えているのに、実際の住民達は環境問題に柔軟に対応しながら、もし被害が悪化したら、隣近所に引っ越すかのように島から島へ移動する、グローバルな世界に生きる人たちであったという。
もちろんこれも一つの側面であり、これまでの狭い見解などを見直しつつ、また更に学問研究は進化していくのでしょうね。
この科目はラジオ授業で、テキストの写真は白黒です。
主任講師の高倉先生の他、4人の先生が分担執筆されていますが、現地調査など、先生方の実体験などを元に書かれている事から、テレビ放送でカラー映像としても見たかったです。
単位認定試験
結果はAで無事合格できました。
択一式で、4問の中から正解を選ぶ形式です。
私が受講した2021年2期は、16問の出題でした。
全体の平均は80点を超えている事もあり、ちゃんとテキストを読めば難易度的には難しくはないはずです。
が、私の場合は3問ほど間違えたので、読み込みが甘かったようです(反省)。
まとめ
ヒト(人)を理解するための科目です。
ヒトに関する諸学問の、知見や考え方を知る事ができます。
次はぜひテレビ放送でお願いしたいです。