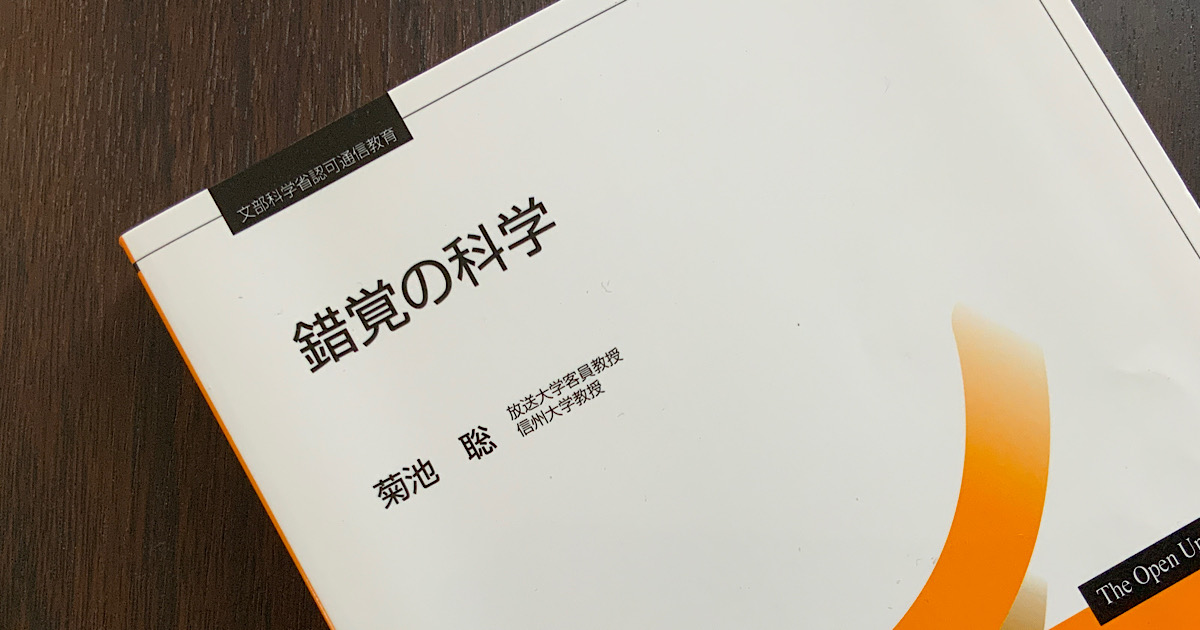面白い評判の授業なので受講してみました。
難しい心理学系の科目の中で、こちらは視覚で見る事ができるので、比較的学びやすいのではないかと思ったのも理由の一つです。
授業概要
この科目では、さまざまな「錯覚」という現象の性質や特徴を学んでいきます。
「錯覚」がいかに私たちの日常生活や社会などに影響を与えるか、人の認知の仕組みについて理解を深め、心理学的なクリティカル・シンキング(対象の本質を捉えて客観的に考える事)の基本を身につけていきます。
| コース・科目 | 心理と教育コース 専門科目 |
| 放送形式 | テレビ放送 45分×15回 |
| 主任講師 | 菊池 聡(信州大学教授) |
| 単位認定試験 | 択一式 |
目次
第1回 錯覚への招待
第2回 視覚の錯覚 見ることは考えること
第3回 錯視の世界を体験する
第4回 知覚心理学と絵画芸術の接点
第5回 視覚芸術と錯覚
第6回 記憶の錯覚 人の記憶は確実なのか
第7回 思考の錯覚と認知バイアス
第8回 ヒューリスティックと行動経済学
第9回 自己の一貫性と正当化が引き起こす錯覚
第10回 身近な情報の錯覚
第11回 錯覚の光と影 エンターテインメントと悪質商法
第12回 原因と結果をめぐる錯覚
第13回 科学的思考と錯覚
第14回 自己の錯覚
第15回 錯覚とメタ認知 錯覚とよいつきあいを築くために
感想
評判どおりとても面白く、受講してよかったです。
さまざまな錯覚を経験しました。
第2章 視覚の錯覚での「部屋の視覚の錯覚」は、わかってはいても「おぉっ」と口から出てしまったり、他の章でも同様に毎回映像や画像の錯覚には驚かされっぱなしでした。
また、第7章 思考の錯覚と認知バイアスでの、”雨乞いしたら雨が降るか”の実験や、第10章 身近な情報の錯覚の、”叱るか褒めるか”の実験もとても面白く、たいへん興味深いものでした。
自分が実際に見えている世界、信じている世界にも、もしかしたらがある。
つまり自分が見えている世界は本当はそうではない可能性もある、ということを科学的なアプローチで結果を知り理解する事ができます。
自分は自分の見えているものを信じ、とにかく自分が正しいと思いがちだけど、そうではない事も多くあるという大変奥深い科目でした。
「より柔軟で多面的なものの見方ができることにより、人と人とがよりよく理解しあえる社会の実現に寄与することを願っている(錯覚の科学P252より)」
というテキスト最終章の一文に、ようやくこの科目の本当の意図と気持ちを理解した未熟者であります。
心理学の入り口として強くお勧めできる科目ですし、受講生ではない方も視聴するだけでも十分楽しめ勉強になる科目です。
ちなみに、主任講師の菊池先生のおだやかで優しい微笑みには癒されますよ。
単位認定試験
結果は◯Aで無事合格できました。(単位認定試験の日程と合格基準点)
択一式で、4問の中から正解を選ぶ形式です。
過去の平均点も80点前後で、難易度は低めです。
「発達科学の先人たち」や、「心理と教育へのいざない」同様、日常の生活では聞くことがない専門用語が多く登場しますので、言葉を頭に叩き込むのは中々大変ですが、授業をちゃんと受けていれば問題自体はそこまで難しくはありません。
まとめ
とても楽しく為になる授業なので、受講をおすすめします。
錯覚というものを科学的に知ることができます。
単位認定試験の難易度は低めです。